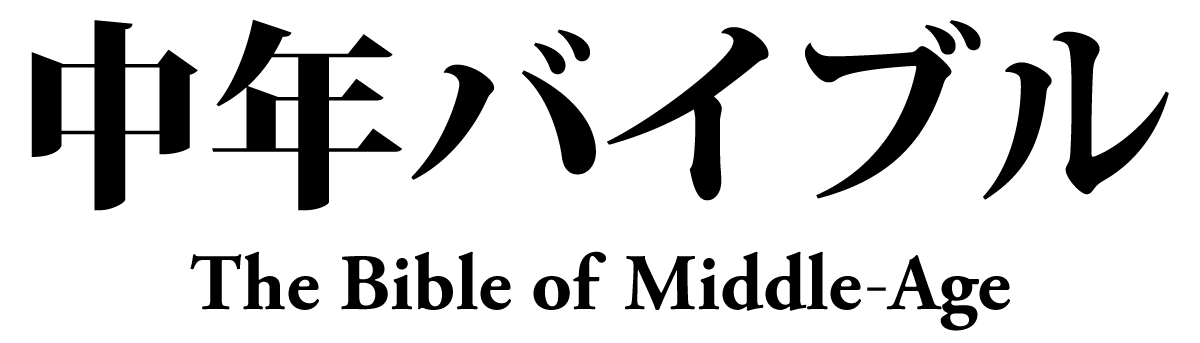私のプロフィール:マサ(48歳)
私は、かつてサッカーにすべてを捧げ、挫折し、その後はビジネスというフィールドで「勝利」だけを追い求めてきました。
しかし40代半ば、私は人生最大の「嵐」に直面しました。
ここでご紹介するお話は、一度人生というピッチから逃げ出そうとし、そこから「自分自身」というチームを愛せるようになるまでの、私の半生の記録です。
泥だらけのヒーローと「エース」の呪縛
私のアイデンティティは、常にサッカー場の土の匂いと共に形成されていました。
小学校2年生でサッカーを始めた私は、幸運なことに恵まれた体格とスピードを持っていました。
FW(フォワード)としてゴールを量産し、チームの「エース」として君臨すること。
それだけが子どもの頃の私にとって、「存在価値のすべて」だったのです。
当時の私にとって、「世界の価値」はあまりにもシンプルなものでした。
●ゴールを決める奴が偉く、決められない奴は価値がない
●結果がすべて。数字がすべて。
この極端な二元論が、幼い私の心に深く刻み込まれました。
中学、高校と上がるにつれ、サッカーはさらに生活のすべてを支配していきました。
「もっと強く、もっと速く、もっと有名に」。
その渇望こそが私のガソリンでした。
しかしこの時すでに、「期待に応え続け、勝ち続けなければ、誰にも愛されない」という見えない呪いが、私の心の中に根を張っていたのです。
国立競技場の夢と、初めて味わった「ベンチの冷たさ」
高校3年生、私は人生で最初にして最大の挫折を経験します。
冬の選手権の予選、私はエースナンバーの「10番」を背負っていましたが、直前の怪我と不調で、準決勝という大舞台でスターティングメンバーから外されたのです。
ピッチの外から試合を眺めるなんて、生まれて初めてのことでした。
泥だらけで戦う仲間たち。
沸き上がるスタンド。
しかし、その中心に自分はいない…
「俺がいないほうが、チームはうまく回っているんじゃないか?」
その恐怖と疎外感は、18歳の私にはとても耐え難いものでした。
結局チームは敗退し、国立競技場の芝を踏むことなく私のサッカー人生は終了。
引退の日、部室の裏で一人で泣きながら、私は自分に誓いました。
「もう二度と、サブ(補欠)にはならない。これからの人生、どんなフィールドでも絶対に主役の座は譲らない」
この歪んだ復讐心が、私をその後20年間にわたる「終わりのない競争」へと駆り立てる原動力となりました。
ビジネスというフィールドでの「ハットトリック」
大学進学後、私はあえてサッカー部には入りませんでした。
なぜなら、「挫折した自分」を直視するのが怖かったからです。
その代わりに、私は「ビジネス」という新しいピッチを見つけました。
都内の私立大学に進学した私は、サッカーで培った負けん気をすべて勉強と就職活動に注ぎ込んだのです。
「努力は裏切らない。勝てば官軍だ」
私はいつの間にか、「弱みを見せず、常に最短距離で正解を選び続けるスマートな自分」という仮面を作り上げつことだけを考えていました。
ただ、ゼミの恩師だけが、私の心の歪みに気づいていたようでした。
「マサくん、君の書く論文は完璧だが、血が通っていない。君はゴールを決めることばかり考えていて、パスを回す喜びや、守備の苦労を忘れているんじゃないか?」
先生は私が隠しきれなかった危うさを感じ取り、心配してくれましたが、当時の私にはその言葉の意味が全く理解できず、ただ「古い世代の小言」として聞き流してしまったのです。
「先生、結果が出なければ、プロセスなんてただのゴミですよ」
私はそう言い放ち、誰よりも早く、誰もが社名を知っている大手IT企業から内定を勝ち取りました。
ビジネスというピッチでの「ハットトリック」
社会に出た私は、まさに無敵でした。
IT業界の激流の中で、私は「サッカー部の練習に比べれば仕事の過酷さなんて大したことはない」と、誰よりも働き、誰よりも成果を出しました。
●20代後半
営業成績でトップを取り、若手最速で主任に昇進。
この頃、最も美しい「サポーター」だと思っていた今の妻と結婚。
●30代前半:
大規模なプロジェクトを成功させ、マネージャー職へ。
都内に3LDKの新築マンションを購入。
●30代後半
年収は1,500万円を超え、SUVを乗り回し、休日には家族でキャンプへ。
私は、高校時代に奪われた「10番」を、ビジネス界で取り戻したつもりでした。
「俺は誰もが羨む『理想の人生』のパズルを、一片のミスもなく完成させている」
当時の私は「正解を掴んだ」と思っていたのでした。
しかし、パズルが完成に近づくほど、心のどこかから「…で、次はそうすればいいの?」という不気味な声が聞こえ始めていたのです。
忍び寄る「正午の影」と、色のない世界
そして44歳を過ぎた頃、ピッチの照明が急に暗くなったような感覚に襲われました。
心理学者が「人生の正午」と呼ぶこの時期、私の世界からは、突如として「色」が失われました。
あんなに追い求めていた昇進も、年収のアップも、ある日を境に全く心が動かなくなったのです。
朝、鏡を見ると、そこには白髪が増え、目の死んだ中年男性が立っている。
「俺は、何のためにこんなに走っているんだ?」
かつてのガソリンだった「渇望」が、いつの間にか空っぽになっていたのです。
さらに、草サッカーに誘われて参加した際、決定的な衝撃を受けました。
頭の中では全盛期のステップを踏んでいるのに、足が全く付いてこない…
20代の若者にいとも簡単に振り切られ、息が切れて動けなくなったとき、私はピッチの隅で激しい吐き気と羞恥心に襲われました。
「俺は、もうピッチに立ってはいけない老兵なのか?」
身体の衰えは、ダイレクトに「死の足音」として聞こえ始めました。
人生には終わりがある。
自分はもう、下降線をたどるだけの存在なのだ…
そんな恐怖が、夜な夜な私を襲いました。
「中年の危機」の深淵で味わった心理的苦痛
48歳になった今、私はようやく、あの数年間の嵐を客観的に見つめることができるようになりました。
今になって振り返ると、「色」や「温度」を失ったあのときの日々は、精神的な「独房」に閉じ込められたようなものだったと。
- 猛烈な焦燥感と逃避願望
今でも何故かはわからないのですが、ある日の仕事中急に心臓がバクバクし、「今すぐここから逃げ出さなければ死んでしまう」という強迫観念に苛まれました。
積み上げてきた地位が「檻」に見え、「すべてを捨てて知らない土地へ行けば楽になるのではないか」という幻想が頭の中に渦巻きました。
- 「エース」のプライドが崩れる痛み
最も辛かったのは、弱さを誰にも見せられないことでした。
マネージャーとして「強い自分」を演じてきた私は、「助けてほしい」という一言がどうしても言えませんでした。
心の中は、今にも崩れそうな「砂の城」だったのです。
再生への転機|恩師の言葉と「ベンチから見る景色」の受容
絶望の底で、私は耐えきれず大学の恩師に電話をかけました。
「先生…… 僕、もう自分が誰なのか、何のために生きているのか、全くわからなくなりました」
そんな重すぎる言葉に対して、恩師は静かに言いました。
「マサくん、今の君はサッカーで言えば『プレイスタイルの変更』を迫られている時期なんだよ。
これまでは『外側の成果』だけで自分を定義してきた。
でも、これからはピッチ全体を見渡して、自分という存在がそこにいること自体を味わったらいい。」
その言葉を聞いたとき、私は生まれて初めて、自分に「負けてもいい」と許可を出せた気がしました。
エースでなくてもいい。
主役でなくてもいい。
「10番のユニフォーム」を脱ぎ捨てた瞬間、私はようやく、深く、長い呼吸ができるようになった気がしました。
アディショナルタイム = 人生の後半戦を自由に生きる
現在、私は48歳。
IT企業の管理職としての仕事を続けていますが、以前のような「出世競争」からは静かに降りました。
今の私の喜びは、部下の成長を一歩引いて眺めることや、地域の少年サッカーチームでボランティアコーチをすることにあります。
子どもたちには、
「ゴールだけが人生じゃない、パスやディフェンスも君たちなりに力一杯やってごらん。
そのプロセス自体がいつか君たちを大きくしてくれるから」
と伝えています。
中年の危機(ミッドライフ・クライシス)は、あなたがこれまで一生懸命に「外向きの正解」を求めて走り続けてきた証拠です。
あなたの魂が、「もう無理をして誰かの期待に応えなくていい。不完全なままの自分を愛しなさい」と告げている、アップグレードの通知なのです。
人生という試合は、ここからが一番深くて、面白い。
今の私は「『エースの座』を降りたからこそ見える美しい景色が必ずある」と思えるようになり、新しい人生・生活を楽しめています。
マサ(48歳)
- 専門領域:ミッドライフ・クライシス(中年の危機)、40代からのメンタルケア、キャリア再定義。
- 趣味:少年サッカーコーチ、DIY、読書(哲学・心理学)。
- 好きな言葉:「成功は決して偶然ではない。しかし、何よりも自分が取り組んでいることへの愛情が必要だ。」